自動車業界は、技術用語、規格、団体名など、多種多様な略語で溢れており、専門家以外には理解が難しい世界です。特に近年はCASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)革命と呼ばれる大変革期を迎えており、新しい略語も続々と登場しています。
この記事では、自動車業界で頻繁に使われる略語を、初級から上級まで網羅的に解説し、それぞれの略語が何を示し、どのような文脈で使用されるのかを丁寧に説明します。自動車業界に関わる方はもちろん、自動車に興味のある方、最新技術を追いかける方にも役立つ情報を提供します。
1. 基本的な自動車用語・機構関連の略語(初級編)
1.1 駆動方式
- FF (Front Engine Front Drive): エンジンを前部に搭載し、前輪を駆動する方式。構造が比較的シンプルで、燃費性能に優れ、室内空間を広く確保しやすいのが特徴です。大衆車で広く採用されています。
- FR (Front Engine Rear Drive): エンジンを前部に搭載し、後輪を駆動する方式。重量バランスが良く、スポーティな走行性能(特にコーナリング性能)が特徴です。高級車やスポーツカーで採用されています。
- MR (Midship Engine Rear Drive): エンジンを車体中央部(前後車軸の間)に搭載し、後輪を駆動する方式。重量バランスが非常に良く、運動性能に優れますが、居住空間や荷室が狭くなりがちです。スポーツカーやレーシングカーで採用されています。
- RR (Rear Engine Rear Drive): エンジンを後部に搭載し、後輪を駆動する方式。独特の走行特性を持ち、かつては小型車で多く見られましたが、現在はポルシェ911などの一部車種に限られます。
- 4WD (Four Wheel Drive) / AWD (All Wheel Drive): 四輪全てを駆動する方式。悪路走破性に優れます。
- パートタイム4WD: 必要に応じて四輪駆動に切り替える方式。燃費を重視する場合に用いられます。
- フルタイム4WD: 常時四輪駆動する方式。安定した走行性能を発揮します。
- AWDはフルタイム4WDの一種と捉えられる場合が多く、電子制御で前後輪へのトルク配分を最適化するシステムを指すことが多いです。
1.2 エンジン関連
- NA (Naturally Aspirated): 自然吸気エンジン。ターボチャージャーなどの過給器を持たないエンジン。エンジンの回転数に応じて出力が線形に変化するため、自然なフィーリングが特徴です。
- TC (Turbo Charger)/T/C: ターボチャージャー。排気ガスのエネルギーを利用してタービンを回し、空気をエンジンに送り込むことで出力を向上させる装置。近年は燃費向上のため、ダウンサイジングターボとして小型エンジンと組み合わせられることが多いです。
- SC (Super Charger)/S/C: スーパーチャージャー。エンジンの回転を利用して空気をエンジンに送り込む装置。ターボチャージャーに比べて低回転域から効果を発揮するのが特徴です。
- 直噴 (Direct Injection)/DI: 燃料を直接燃焼室に噴射する方式。燃焼効率の向上に貢献し、燃費と出力の両立に貢献します。
- HV (Hybrid Vehicle): ハイブリッド車。ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせた車両。燃費性能の向上や排出ガスの低減に貢献します。
- ストロングハイブリッド: モーターのみでの走行も可能なハイブリッドシステム。
- マイルドハイブリッド: モーターはエンジンのアシストが主な役割のハイブリッドシステム。
- EV (Electric Vehicle)/BEV: 電気自動車。電気モーターのみで走行する車両。走行中に排出ガスを出さないのが特徴です。
- PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): プラグインハイブリッド車。外部電源から充電可能なハイブリッド車。短距離走行はEVとして、長距離走行はハイブリッド車として使用できます。
- FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle)/FCV: 燃料電池電気自動車。水素と酸素の化学反応を利用して発電し、モーターで走行する車両。排出するのは水のみというクリーンなエネルギー源として注目されています。
1.3 変速機関連
- AT (Automatic Transmission): 自動変速機。自動的にギアチェンジを行う変速機。運転操作が容易になります。
- MT (Manual Transmission): 手動変速機。ドライバーが手動でギアチェンジを行う変速機。ダイレクトな操作感やエンジンのレスポンスを楽しめます。
- CVT (Continuously Variable Transmission): 無段変速機。ギア比を無段階に変化させる変速機。滑らかな加速と燃費性能の向上に貢献します。
- DCT (Dual Clutch Transmission): デュアルクラッチトランスミッション。奇数段と偶数段のギアをそれぞれ別のクラッチで制御する変速機。素早い変速とダイレクトなフィーリングを両立します。
1.4 シャシー・足回り関連
- ABS (Anti-lock Brake System): アンチロックブレーキシステム。急ブレーキ時にタイヤのロックを防ぎ、操舵性を維持する装置。安全運転に不可欠な装置です。
- ESC/ESP (Electronic Stability Control/Program): 横滑り防止装置。車両の横滑りを検知し、ブレーキやエンジン出力を制御して車両の安定性を保つ装置。メーカーによって名称が異なる(例:トヨタ:VSC、日産:VDC)。
- TCS/TRC (Traction Control System): トラクションコントロールシステム。タイヤの空転を検知し、エンジン出力を制御して駆動力を確保する装置。滑りやすい路面での発進や加速を補助します。
- ADAS (Advanced Driver Assistance Systems): 先進運転支援システム。衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報、アダプティブクルーズコントロールなどの運転支援技術の総称。自動運転技術への過渡期の技術として注目されています。
- ACC (Adaptive Cruise Control): アダプティブクルーズコントロール。先行車との車間距離を維持しながら走行する機能。高速道路などでの運転疲労軽減に貢献します。
- LKA/LDW (Lane Keeping Assist/Lane Departure Warning): 車線維持支援/車線逸脱警報。車線からの逸脱を検知し、ドライバーに警告したり、ステアリング操作を支援したりする機能。
- サスペンション (Suspension): 車輪と車体を繋ぎ、路面からの衝撃を緩和する装置。乗り心地や操縦安定性に影響します。
- ストラット (Strut): サスペンション形式の一つ。簡素な構造で、小型車に多く採用されています。
- マルチリンク (Multi-link): サスペンション形式の一つ。複雑な構造で、高い運動性能を発揮します。
1.5 その他技術用語
- ECU (Electronic Control Unit): 電子制御ユニット。エンジン、ブレーキ、トランスミッションなどの各部を電子的に制御する装置。現代の自動車には多数のECUが搭載されています。
- CAN (Controller Area Network): 車載ネットワーク規格の一つ。ECU間のデータ通信に使用される。
- OEM (Original Equipment Manufacturer): 純正部品製造業者。自動車メーカー自体を指します。
- Aftermarket: 社外部品市場。純正品以外の部品やアクセサリーなどを扱う市場。
- VIN (Vehicle Identification Number): 車両識別番号。車台番号とも呼ばれ、車両一台一台に割り当てられた固有の番号。
- OBD (On-Board Diagnostics): 車載式故障診断装置。車両の異常を検知し、故障診断を容易にするシステム。
2. 自動車業界特有の略語(中級編)
2.1 開発・生産関連
- PV (Production Vehicle): 量産車。実際に販売される車両。
- 試作 (Prototype): 量産前の試作車。デザインや性能の検証、走行テストなどに使用されます。
- ASSY (Assembly): アッセンブリー。複数の部品を組み付けた状態のもの。
- 大日程 (Grand Schedule): 車両開発全体のスケジュール。開発期間や各工程のスケジュールなどが含まれます。
- Tier1 (Tier One Supplier): 自動車メーカーに直接部品を供給する一次サプライヤー。
- Tier2 (Tier Two Supplier): Tier1サプライヤーに部品を供給する二次サプライヤー。
- プラットフォーム (Platform): 車両の基本構造。エンジン、シャーシ、サスペンションなどを共有する複数の車種を効率的に開発するための共通基盤。
- キャリーオーバー (Carry Over): 既存の部品や技術を新しい車種に流用すること。開発コストや期間の削減に貢献します。
- フルモデルチェンジ (Full Model Change/FMC): 車種の大幅な改良。外観デザイン、基本性能、メカニズムなどが全面的に刷新されます。
- マイナーチェンジ (Minor Change/MC): 車種の一部改良。外観デザインの一部変更や装備の追加などが行われます。
- イヤーモデル (Year Model/YM): 年次改良モデル。毎年行われる小規模な改良。
- コンセプトカー (Concept Car): 将来の技術やデザインの方向性を示すための試作車。モーターショーなどで発表されます。
- ショーモデル (Show Model): モーターショーなどで展示される車両。市販予定のないものも含まれます。
- CKD (Completely Knocked Down): 部品を全て分解した状態で輸出・輸入すること。現地生産を行う際に用いられます。
- CBU (Completely Built Up): 完成車を輸出・輸入すること。
2.2 品質・評価関連
- DV (Design Verification): 設計検証。設計段階での性能や品質の検証。シミュレーションや実験などが行われます。
- PV (Performance Verification): 性能検証。試作車や量産車での性能評価。実走行テストや各種試験などが行われます。
- QC (Quality Control): 品質管理。製品の品質を維持・向上するための活動。
- QA (Quality Assurance): 品質保証。顧客に提供する製品の品質を保証するための活動。
- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): 故障モード影響解析。製品の故障モードとその影響を分析する手法。
- FTA (Fault Tree Analysis): フォールトツリー解析。故障の原因を系統的に分析する手法。
2.3 法規・規格関連
- ECE (Economic Commission for Europe): 欧州経済委員会。自動車の安全基準などを定めている。
- JIS (Japanese Industrial Standards): 日本工業規格。日本の工業製品に関する規格。
- ISO (International Organization for Standardization): 国際標準化機構。国際的な規格を策定している。
- Euro NCAP (European New Car Assessment Programme): 欧州の新車アセスメントプログラム。車両の安全性を評価する機関。
- JNCAP (Japan New Car Assessment Program): 日本の新車アセスメントプログラム。車両の安全性を評価する機関。
2.4 その他
- CASE (Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric): 自動車産業のトレンドを表すキーワード。コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化を意味する。
- MaaS (Mobility as a Service): モビリティサービス。複数の移動手段を統合的に提供するサービス。
- OEM (Original Equipment Manufacturer): 受託製造。他社ブランドの製品を製造すること。
- ODM (Original Design Manufacturing): 受託設計製造。他社ブランドの製品を設計から製造まで行うこと。
3. 電動化・コネクティッドカー関連の略語(上級編)
3.1 電動化関連
- BEV (Battery Electric Vehicle): バッテリー式電気自動車。
- HEV (Hybrid Electric Vehicle): ハイブリッド電気自動車。
- PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): プラグインハイブリッド電気自動車。
- FCV (Fuel Cell Vehicle): 燃料電池自動車。
- ZEV (Zero Emission Vehicle): 排出ガスゼロの自動車。
- HV (High Voltage): 高電圧。電気自動車やハイブリッド車で使用される高電圧システム。
- EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment): 電気自動車用充電設備。
- BEV (Battery Electric Vehicle): バッテリー電気自動車
- Li-ion (Lithium-ion): リチウムイオン電池。電気自動車に広く使用されている電池。
- 駆動用バッテリー (Traction Battery): 電気自動車の走行用モーターに電力を供給するバッテリー。
- インバーター (Inverter): 直流電力を交流電力に変換する装置。モーター制御に必要。
- 回生ブレーキ (Regenerative Braking): ブレーキ時にモーターを発電機として利用し、運動エネルギーを電気エネルギーに変換してバッテリーに充電するシステム。
- 急速充電 (DC Fast Charging): 短時間でバッテリーを充電する方法。
- 普通充電 (AC Charging): 家庭用コンセントなどを使用した充電方法。
3.2 コネクティッドカー関連
- V2X (Vehicle to Everything): 車両とあらゆるものとの通信。
- V2V (Vehicle to Vehicle): 車両間通信。
- V2I (Vehicle to Infrastructure): 車両と道路インフラ間の通信。
- V2P (Vehicle to Pedestrian): 車両と歩行者間の通信。
- OTA (Over-The-Air): 無線ネットワーク経由でのソフトウェアアップデート。
- IVI (In-Vehicle Infotainment): 車載インフォテインメントシステム。
- Telematics (テレマティクス): 通信技術を利用した情報提供サービス。
- CAN (Controller Area Network): 車載ネットワーク規格の一つ。ECU間のデータ通信に使用される。
- LIN (Local Interconnect Network): CANよりも簡易な車載ネットワーク規格。
- Ethernet (イーサネット): 車載ネットワークに使用される高速通信規格。
4. 最近注目されている略語(最先端編)
- SDV (Software Defined Vehicle): ソフトウェア定義自動車。車両の機能や性能をソフトウェアによって制御する概念。
- AI (Artificial Intelligence): 人工知能。
- 生成AI (Generative AI): 既存のデータから新しいデータを生成するAI。
- ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems): 先進運転支援システム。
- LiDAR (Light Detection and Ranging): 光を用いた距離測定技術。自動運転などに使用される。
- SoC (System on a Chip): 複数の機能を統合した集積回路。車載コンピュータなどに使用される。
- ECU (Engine Control Unit): エンジン制御ユニット
- TCU (Transmission Control Unit): 変速機制御ユニット
- BCM (Body Control Module): 車体制御モジュール
- VCU (Vehicle Control Unit): 車両制御ユニット。車両全体の制御を行う。
- ADAS ECU (Advanced Driver Assistance Systems Electronic Control Unit): 先進運転支援システムを制御するECU。
- Autonomous Driving (自動運転):
- レベル1: 運転支援(例:ACC)
- レベル2: 部分自動運転(例:ACCと車線維持支援の組み合わせ)
- レベル3: 条件付き自動運転(特定の条件下でシステムが運転操作を行う)
- レベル4: 高度自動運転(特定の条件下でドライバーの操作なしにシステムが運転操作を行う)
- レベル5: 完全自動運転(あらゆる条件下でドライバーの操作なしにシステムが運転操作を行う)
- HD Map (High Definition Map): 高精度地図。自動運転に必要不可欠な情報を含む地図。
- センサー (Sensor):
- カメラ (Camera): 画像認識に使用
- レーダー (Radar): 電波を用いた距離測定
- ソナー (Sonar): 超音波を用いた距離測定
- LiDAR (Light Detection and Ranging): レーザー光を用いた高精度な距離測定
- サイバーセキュリティ (Cyber Security): 車両の電子システムに対する不正アクセスや攻撃を防ぐための対策。
- OTA (Over-the-Air): 無線通信によるソフトウェア更新。
5. まとめ
本記事では、自動車業界で頻繁に使用される略語を幅広く解説しました。これらの略語を理解することで、自動車関連の記事や技術文書、業界関係者とのコミュニケーションがスムーズになるでしょう。技術革新が著しい自動車業界では、今後も新しい略語が登場することが予想されます。常に最新の情報にアンテナを張り、知識をアップデートしていくことが大切です。
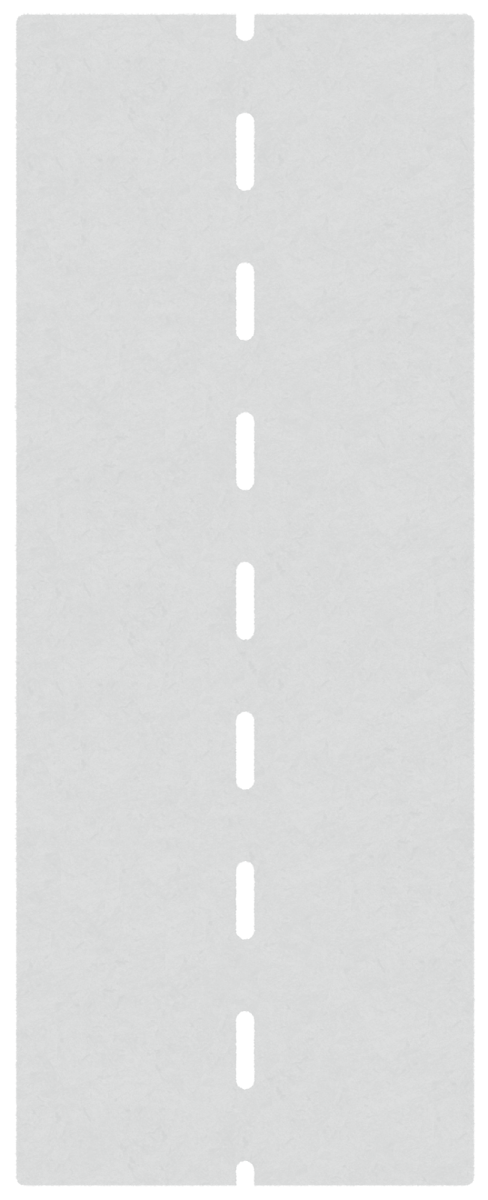


コメント